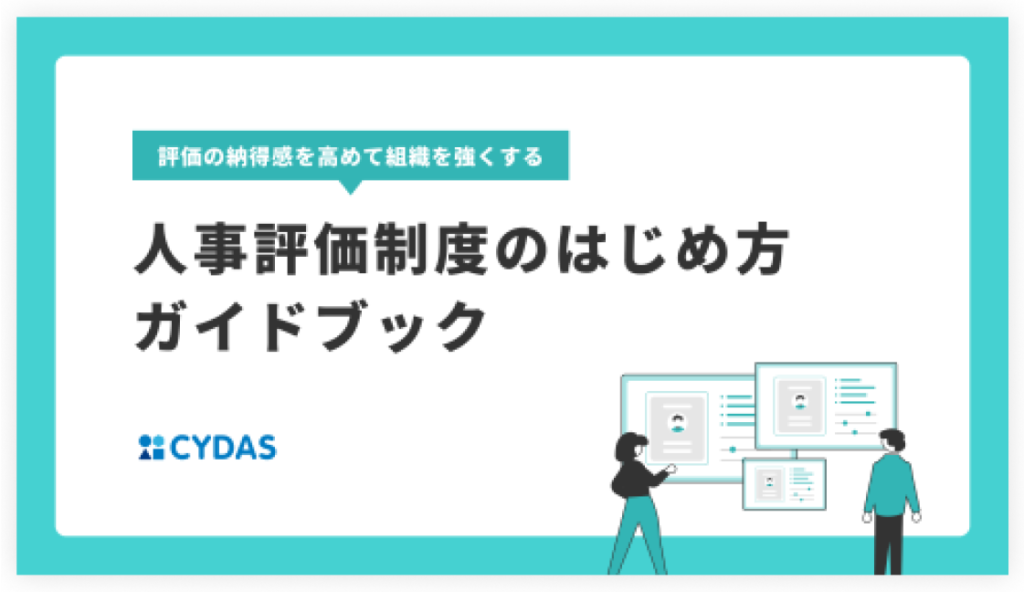2022.3.22
中小企業こそ人事評価システムを導入すべき理由とは|メリットや選び方を紹介
「人事評価がうまくできていない」「評価に対して不満を抱いている従業員が多い」といった悩みを抱えている人事担当者のなかには、人事評価システムの導入を検討している人も少なくないはずです。
そこで今回は、自社にとって必要なものかどうかを判断できるよう、中小企業における人事評価システム導入のメリットや効果について解説します。さらに、システムを選ぶポイントや人事評価制度の作成・運用する重要なポイントも紹介するので、あわせて参考にしてみてください。
サイダス社が提供する人材データプラットフォーム「CYDAS」は、タレントマネジメントの機能も兼ね備えた人事評価システムです。人材情報の一元化、評価、1on1、フィードバックまで1つのシステムで完結できます。

目次
人事評価システムが中小企業に必要な理由とは?

人事評価システムが中小企業に必要な理由を説明する前に、まずは人事評価システムの概要について解説します。
そもそも人事評価システムとは?
人事評価システムとは、従業員を評価する際に必要となる情報をシステム上で管理・運用するツールのことです。
人事評価システムの機能は、主に次の4つです。
【人事評価システムの主な機能】
- 評価のプロセスや結果を可視化する
- 紙やExcelで管理していた評価シートをシステム化する
- システム上に構築したデータを出力する
- (クラウド型の場合)社内・社外問わずどのような場所でも利用できる
人事評価自体はもともと紙媒体やExcelなどを用いて行われてきましたが、システム上で管理・運用して「見える化」することで、不正な評価が起こりにくくなります。データをもとに評価するため、主観による評価ではなく公平な評価を効率よく行えるようになるのです。
また、人事評価システムによっては、従業員のスキルを管理できるものもあります。従業員一人ひとりのスキルや業績などの情報をもとに、人事異動や新規プロジェクト発足時に適切な人材配置が可能になるのもポイントです。さらに、今の従業員に足りないスキルが分かるので、人材確保の計画時にも役立ちます。
人事評価システムについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▼評価情報を「見える化」するなら、「CYDAS」▼
中小企業にこそ人事評価システムが必要な理由
中小企業のなかには、社長自らが現場に出ていくことを好み、その結果「社長の代わりを果たせる人材が育たない」「経営に専念できない」という重大な課題が生じることがあります。社長の手腕に頼りきりでは、持続可能な組織運営は難しいため、優秀人材の確保(採用)と既存社員の人材育成が必要不可欠です。中小企業は、大企業に比べて従業員1人あたりの影響力が大きいからこそ、人事評価システムが必要なのです。
例えば、従業員数10人の企業において1人の生産性が低下した場合、単純に考えると業務の10%に支障が出ることになります。一方、1,000人の企業の場合は、1人の生産性が低下しても業務に支障が出るのはわずか0.1%ほどです。従業員数が少ない企業ほど、1人あたりの影響力が大きいのは明らかです。
裏を返すと、中小企業で従業員のモチベーションが向上すれば、業績アップに直結しやすいと考えられます。幸いなことに、昨今は、クラウド型の人事評価システムが増えつつあり、料金的にも導入しやすくなっています。中小企業こそ人事評価システムを導入し、従業員の意識を高める取り組みを実施するべきでしょう。
中小企業が人事評価システムを導入する目的
中小企業が人事評価システムを導入する目的は、以下のとおりです。
業務効率化
人事評価に関連する業務は、評価シートの作成・配布、回収、データ集計、給与・賞与への反映など、複雑で多岐にわたり、手作業での運用は誤りやミスのリスクが高くなります。紙やExcelなどで運用している場合、従業員の記入漏れの確認・差し戻しの対応が発生するほか、シートの管理も煩雑になりやすく、人事担当者の負担になることも少なくありません。しかし、人事評価システムを導入することで、以下のような業務効率化が期待できます。
【人事評価システム導入による業務効率化の例】
- 記入漏れや誤りのない状態で評価シートを提出してもらえる
- 評価の進捗状況がステータス管理で一目でわかる
- 評価データの自動集計ができる
人材育成や異動配置への活用
中小企業では、紙やExcelで人事評価を実施しているケースも少なくありません。しかし、評価の履歴(変遷)が視覚的にわかりづらい、人材育成や異動配置に評価データを効果的に活用できないなどの課題があります。
人事評価システムの導入により、従業員の評価データのほか、スキル・資格情報や異動履歴などのデータを一元管理し掛け合わせた活用が可能になり、人事担当者や経営層の勘に頼らないデータドリブンな人材育成や異動配置が実施できます。
中小企業が人事評価システムを導入するメリット

中小企業が人事評価システムを導入すると、以下のメリットが得られます。
【人事評価システムの導入メリット】
- 従業員のスキルが可視化される
- 公平な人事評価につながる
- 人事評価にかかる工数やコストが削減できる
- 従業員のモチベーションが上がり離職率の低下につながる
それぞれ詳しく解説します。
従業員のスキルが可視化される
人事評価システムでは、従業員のスキルやこれまでの経歴、評価履歴などが一元管理されます。従業員のスキルや能力が可視化されることで、異動や育成など人材配置におけるさまざまなシーンに役立てられます。
例えば、新規プロジェクトに関するメンバー選出の際、人事評価システムがあれば、必要な資格や経験などから人材を的確に抽出できるようになります。
従業員のスキルが可視化され、適材適所な人材配置が可能になれば、業務は効率よく進むようになるでしょう。また、人事情報は経営戦略や事業計画にも役立つので、うまく活用できれば業績アップも期待できます。
公平な人事評価につながる
人事評価システムを導入すると、人事評価が公平になります。評価基準やプロセスが明確化されることで統一できるようになるため、好き嫌いなど上司の主観による不明瞭な評価が付けられる心配がありません。
明確な基準が統一されると、従業員が評価への納得感を得やすくなるのもポイントです。「結果を出しているのに評価されない」など、従業員の会社に対する不信感を払拭することにつながります。客観性のある評価が可能になれば、従業員の意識レベルも高まるはずです。
人事評価にかかる工数やコストが削減できる
導入目的の部分でも触れたとおり、人事評価を紙やExcelなどで管理していた企業にとっては、システムの導入は人事評価にかかる工数やコストの削減につながります。
紙やExcelで管理する場合、評価シートの配布から始まり、回収・データの集計・入力・分析とさまざまな工数を踏まなければいけません。全従業員が対象となれば、人事評価にかかる手間と時間は相当なものとなるでしょう。また、場合によっては紙の紛失や入力ミスなどヒューマンエラーが起こる恐れもあります。
人事評価システムを導入することで、今まで手作業で行っていた作業をシステム上で完結できます。人事評価にかかっていた時間を別の業務に活用できるので、業務効率化にもつながるのがポイントです。特に、人材不足が課題となっている企業ほどメリットは大きいといえます。
従業員のモチベーションが上がり離職率の低下につながる
人事評価システムの導入により評価の納得性が高まると、従業員は目標を定めやすくなります。「何をすると評価が上がるのか」が明確になるので、従業員がこれまでよりも意欲的に仕事に取り組もうとするはずです。仕事内容の品質や生産性が向上することで従業員のモチベーションが上がると、離職率の低下につながります。
また、人事評価システムが適切に運用されると、従業員の能力に合わせて目標設定ができるので、業務の進捗度や業務達成までの過程を適切に踏めるようになるのも魅力です。さらに、定期的なフィードバックを行うことで、従業員のモチベーションの維持も図れます。
タレントマネジメントシステム「CYDAS」は、中小企業の公正な人事評価を実現します。
中小企業が人事評価システムを選ぶうえで重要な5つのポイント

人事評価システムによって、特徴や利用できるサービスは異なるものです。そこで、自社に適した人事評価システムを選べるよう、押さえておきたい重要なポイントを紹介します。
【人事評価システムの選定ポイント】
- 自社の人事評価制度に適しているか
- クラウド型かオンプレミス型か
- 目的や実現したいことに合ったシステムを選ぶ
- 人事担当者・従業員の双方にとって使いやすいシステムを選ぶ
- サポート体制が充実しているか
1. 自社の人事評価制度に適しているか
中小企業においては、評価制度がない、または制度はあるがうまく運用に乗っていないというケースも少なくありません。人事評価システムを選ぶ際は、導入目的を明確にしたうえで、自社で取り入れている評価方法、または取り入れたい評価方法に対応していることを確認しましょう。
自社の人事評価制度に適していないと、使い勝手が悪く、うまく活用できない恐れがあります。そうなると、評価方法を一から変えることになり、業務効率化を図るどころか余計な工数を増やし兼ねません。
まずは、自社に適した人事評価制度を見極めることが重要です。下記にて代表的な人事評価方法を紹介するので、参考にしてみてください。
組織における代表的な人事評価方法を紹介
人事評価方法としてよく用いられているのは、以下の5つです。
・OKR
会社が達成するべき目標をもとに、各部門・各従業員の目標を設定し、成果によって評価する方法です。組織が成長することを主眼としているため、目標の達成難易度は高めに設定されます。
・MBO(目標管理制度)
会社規模を問わず、多くの企業で取り入れられている評価方法です。従業員と上司が話し合って個人またはグループの目標を設定し、達成度を各々で管理します。OKRよりも目標の達成難易度は低めです。
・コンピテンシー評価
高い成果を上げている従業員の行動特性を評価基準にする評価方法です。ロールモデルが存在することで、「どのような行動をとると評価されるのか」が明確になります。
・1on1
上司と部下が1対1で行うミーティングです。部下が抱える悩みや課題を把握し、上司は助言することで信頼関係を構築しながら、部下の成長を促します。
・360度評価
1人の従業員に対して、さまざまな立場の人が複数人で評価する方法です。同僚や部下など、さまざまな視点から評価されるので、より公平な評価を付けられます。
2. クラウド型かオンプレミス型か
人事評価システムの形態には、主に「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。それぞれが持つ特徴、そしてかかる費用を見比べながら、どちらが自社に適しているのか判断するようにしましょう。
まずクラウド型は、インターネットを通じて利用する人事評価システムです。インターネット上のサーバーを利用するため、ネット環境があればどの端末からでも利用できます。設備投資がかからないうえに、短期間での導入が可能です。
また、自動でバックアップされるので、データが失われる心配もありません。ただし、カスタマイズ性は高くないので、使い勝手をよくするために仕様変更をしたい企業にとっては、不便に感じる恐れがあります。
一方、オンプレミス型は専用サーバーを自社で導入し、一からシステムを作り上げる人事評価システムです。自社の業務や雇用形態に合わせたシステムを構築・運用できるので、カスタマイズ性が高いところが最大の特徴です。ただし、初期費用が高額になりやすく、システム構築にも時間がかかります。
3. 目的や実現したいことに合ったシステムを選ぶ
人事評価システムを導入する際は、導入する目的を明確にしなければいけません。企業によって抱える課題はさまざまなので、経営理念の浸透や人材育成、コスト削減など、人事評価制度システムを取り入れる目的を見定めましょう。
目的や実現したいことが明確になれば、それに合ったシステムを選定します。適切なシステムを選ぶことで、抱えている課題の早期解決につながるでしょう。
4. 人事担当者・従業員の双方にとって使いやすいシステムを選ぶ
システムを導入しても、人事担当者の負担がかえって増えることになれば、導入するメリットがありません。また、従業員にとって使いづらいシステムは、ストレスを与えることにつながります。人事評価システムを選ぶ際は、双方にとって使いやすいかどうか吟味することも大切です。
例えば、操作画面がシンプルな作りであれば、マニュアルを読まなくても感覚的に操作できます。たくさんの業務を抱えている従業員にとっては、マニュアルを読む時間すらおしいものです。必ずデモ画面やトライアルなどで操作性を確認してから導入を進めましょう。
5. サポート体制が充実しているか
サポート体制が充実している人事評価システムなら、便利なうえに万が一のときに備えておくことができます。例えば、システムの無償アップデートがあると、最新版が更新されたとき、操作なしで自動でアップデートされます。業務に支障が出ることなく、常に最新版を利用できるので、人材が不足している企業も導入しやすいでしょう。
他にも、問い合わせ対応や人事評価制度の企画をお手伝いするサービスなどもあります。自社の状況に合わせ、どのようなサポート体制があるとよいのか、見極めることがポイントです。
また、サポート体制だけでなく、セキュリティ対策にも目を向けておくとよいでしょう。第三者のサイバー攻撃からデータを守れるようになるので、安心して運用できます。
タレントマネジメントシステム「CYDAS」は、システム導入時の煩雑なデータ投入作業をサポートする「導入支援サポート」や、利用開始後もヘルプサイト、電話、メール、zoomなどで不明点を解消できるサポート体制が充実しており、中小企業の方におすすめです。詳細は、「サポートについて」をご確認ください。
人事評価システム導入までの流れ

人事評価システムを導入するために必要な工程は以下の5ステップです。
①導入目的の整理と必要な条件の洗い出し
システムの選定ポイントでも述べたとおり、人事評価システム導入を成功に導くポイントは「自社のニーズや目的にマッチしているか」です。システムベンダーとの打ち合わせの前に、まずは自社の課題や目的・目標を整理し、必要な要件を洗い出しましょう。「いつまでに」「なぜ」など、5W1Hのフレームワークを活用して考えるのもよいでしょう。
②ベンダーやシステムの選定
要件が見えてきたら、webサイトや製品比較サイトなどで複数のシステムベンダーを比較検討しましょう。資料やデモ、トライアルなどを活用して、操作性や機能を確認しましょう。
③システムのカスタマイズと導入作業
システムによっては、自社の要件にあった形で機能をカスタマイズできることがあります。認識のズレがないよう、しっかりと希望を伝えましょう。
タレントマネジメントシステム「CYDAS」なら、システム導入時の煩雑な人事データの投入作業もまるっとお任せできます。
④オンボーディング
導入が完了したら、システムを実際に利用する人事担当者や管理者などに対して、操作説明や機能の理解促進など、オンボーディングを実施します。
⑤運用・保守
ここまで来れば、あとは実際にシステムを利用しながら人事評価を運用しましょう。紙・Excelでの管理から初めてシステムを導入する場合は、多くの疑問や不明点が出てくることも少なくありません。システムの選び方のポイントでも述べたとおり、導入後のサポート体制が充実している企業を選ぶと良いでしょう。また、より発展的な活用方法を学びたい場合は、イベントやセミナー、ユーザー同士の交流会などを定期的に開催している企業もおすすめです。
人事評価システムならCYDAS

人事評価システムを導入することで得られる効果は、中小企業ほど大きいものです。中小企業は、従業員1人あたりの働きが与える影響力が大きいため、公平に評価できる環境がとても重要です。納得性の高い評価ができれば、従業員のモチベーション向上や離職率の低下につなげられます。
しかし、カスタマイズ性や料金など、人事評価システムによって異なる部分が多く、自社に適したシステムを見極めるのは困難です。そこで今回おすすめするのが、使いやすく効果的な人事評価を可能とするタレントマネジメントシステム「CYDAS」です。
CYDASの操作画面は、全従業員が使いやすいようシンプルに作られています。また、従業員同士のコミュニケーションを活性化するため、リアルタイムでの通知や社内広報への絵文字でのリアクションなど、さまざまな仕掛けが施されているのも魅力です。
他にも、異動計画に役立つ配置シミュレーションやいつでも相談できるサポート対応など、さまざまな機能が満載です。CYDASのことをさらに詳しく知りたい方は、気軽にお問い合わせください。
中小企業における人事評価の現状や課題を事例と共に解説

ここまで、人事評価システムの概要や中小企業が導入するうえでのポイントなどについて見てきました。人事評価システム導入には、人事評価制度の構築や課題の整理が重要です。
ここからは、中小企業における人事評価制度の現状や抱えている課題について解説します。
【中小企業における人事評価制度の課題】
- 人事評価制度の導入率が低い
- 人事評価制度が正しく運用されていない
- 人事情報の蓄積がなく人材配置がうまくいかない
- 正しく人事評価ができず離職率が高い
人事評価制度の導入率が低い
厚生労働省によると、人事評価制度の導入率は従業員数100人以下の企業で39.4%、従業員数100人以上の企業では73.7%であると報告されています。規模の小さい企業ほど、人事評価制度の導入率が低いのは明らかです。
多くの中小企業では、深刻な人材不足に悩まされています。人材評価制度は、人材不足の課題を解決する施策の1つでもありますが、そもそも導入ができていない中小企業が少なくありません。
また、人事評価制度を導入していない企業は、従業員自らが自分の能力や会社への貢献度を客観的に把握する機会がありません。何を目標にして頑張ればよいのか分からず、仕事に対するモチベーションや生産性の低下にもつながる恐れがあります。
参考:厚生労働省「令和元年度能力開発基本調査」
人事評価制度が正しく運用されていない
人事評価制度は、正しく運用されてこそ期待できる効果が得られるものです。しかし、せっかく人事評価制度を導入しているにも関わらず、うまく運用できていない中小企業も多い点は課題です。
正しく運用されていない原因の1つに、評価者側のスキル不足が挙げられます。例えば、評価基準に一貫性がなかったり、好き嫌いなどの主観が混ざったりすると、従業員は人事評価に不平や不満を抱くでしょう。モチベーションの低下や離職につながりやすくなります。
企業に評価者を育てるスキルがなければ人事評価制度を正しく運用できないため、評価者側に一定のスキルとそのための教育環境が必要となります。
人事情報の蓄積がなく人材配置がうまくいかない
人事評価の運用が不十分な中小企業では、人事情報の蓄積がなく、適切な人材配置が行えていない課題もあります。適切に人材配置をするためには、従業員一人ひとりのスキルや経験を把握することが必要です。
人事情報の一元管理ができなければ誰がどのようなスキルを持っているのか分からず、異動や新規プロジェクト立ち上げ時のメンバー選びにおいて適材適所が実現できません。
適切な人材配置を可能にするためには、人事評価システムを用いて従業員全員のスキルやこれまでの経歴、適正やポテンシャルなどを分かりやすく一元管理し、可視化することが重要です。
正しく人事評価ができず離職率が高い
人事評価制度を導入していない中小企業は、正しく人事評価できていない可能性があります。評価基準や明確な根拠を従業員に示せていなければ、評価への納得感は得られず、従業員のモチベーションは下がる一方です。特に、優秀な人材や若手従業員は、納得できる評価がもらえないと不満を持ち、離職する可能性が高まります。
ただでさえ人材不足が深刻な中小企業にとって、育成してきた人材や優秀な人材の離職は大きな痛手となるでしょう。企業は従業員に対し、納得性のある人事評価を示すことが重要です。
中小企業が人事評価制度を作成・運用するうえで重要なポイント

人事評価システムを導入しても、うまく活用できなければ意味がありません。そこで、人事評価制度を作成・運用するうえでの重要なポイントを5つ紹介します。
【人事評価制度構築の5つのポイント】
- 企業理念や事業計画に結びついた評価制度を作る
- 公平性や透明性を意識して運用する
- 本人へ評価内容の詳細を開示してシェアする
- 本人へ評価内容の詳細を開示してシェアする
- 柔軟に変化させる
企業理念や事業計画に結びついた評価制度を作る
人事評価の内容は、企業理念や事業計画と結びついていなければいけません。事業と一貫性のない人事評価制度では、何を基準に評価されているのかがあやふやとなり、従業員の納得感が得られにくくなります。
企業理念や事業計画に結びつけるためには、従業員が目標を設定する際に、所属している部署の目標を達成するための目標を立てるのがポイントです。部署の目標を達成する取り組みが認められれば、企業に貢献していると判断され、正当な評価を得られます。
公平性や透明性を意識して運用する
人事評価制度は、公平かつ透明性のある状態で運用することが大切です。立てた目標に対し、どのくらい達成すればよいのか数値で表すと分かりやすくなります。例えば、達成率30%でC判定、50%でB判定、70%以上でA判定というように明確な基準を示してあげるとよいでしょう。そして、この基準はすべての従業員が把握しておくことが重要です。
上司の主観で評価されていないことを理解してもらえるので、従業員は不平や不満を抱きにくくなります。
本人へ評価内容の詳細を開示してシェアする
本人へ評価結果だけを伝えても、納得感は得られにくいものです。「なぜA判定ではなくB判定だったのか?」という疑問が残ってしまう恐れがあります。評価に対してしっかり納得してもらうためには、内容や詳細を伝えることが重要です。
評価の低い部分を把握できれば、自分に足りないものや努力が必要なことを知ることができます。評価内容をもとに上司からフィードバックをもらえれば、具体的にどんな取り組みをすればよいのか分かるでしょう。コミュニケーションの活性化にもつながりますし、努力によって評価が上がれば、従業員のモチベーションも向上します。
評価に応じた報酬を用意する
評価に応じてどのような報酬が得られるのかを明示することも大切です。例えば、「売上を10%アップさせたら報奨金が10,000円もらえる」「担当の新入従業員が目標を30%達成できるよう育成できたらマネージャーに昇進」など、具体的に報酬を決めておきましょう。
目標を達成すると確実に得られる報酬があることを従業員に示すことで、人事評価に対する信頼感を高められます。また、従業員は目標を達成しようと努力するため、モチベーションが向上します。結果的には、企業の業績アップへとつながるでしょう。
柔軟に変化させる
人事評価制度は運用ルールに基づいて活用されるものですが、規模の小さい企業は柔軟性を持たせたほうが効果的です。中小企業の場合、変更事項や突発的な事象が起きやすいうえ、小回りを効かせて動かなければいけないことが多々あります。ある程度柔軟性を持たせておかないと、かえって非効率になることもあるのです。
例えば、採用したい優秀な人材がいれば、給与テーブルから多少外れても高い給与額を提示できるようにしておくなど、柔軟性を持ったルールを設けておくことが重要です。魅力的な報酬を提示ができないと優秀な人材を逃してしまいますが、例外的なものを作っておけば、臨機応変に対応できます。
まとめ
ここまで、中小企業こそ人事評価システムの導入がおすすめな理由、選び方のポイントのほか、人事評価制度についてもご紹介しました。製品比較サイト等で調査を進めていくうちに、単なる機能比較でシステムを選定してしまい、実際に使用してみたら自社の運用と合わなかったという失敗例も少なくありません。人事評価システムの導入において何よりも大事なのは自社の導入目的の整理と運用フローとの親和性です。デモやトライアルなどを駆使して、最適な人事評価システムを選びましょう。
サイダス社が提供する「CYDAS」は、現在お使いの評価シートをそのままシステム化できる再現性に優れた人事評価システムです。MBO、360度評価、コンピテンシー評価などさまざまな評価制度に対応しており、職種ごとに異なる評価制度を用いることも可能です。閲覧権限設定も柔軟性が高く、複雑な評価フローを実行しているお客様でもご利用いただけるシステムです。
資料は無料でダウンロードできますので、お気軽にお問い合わせください。
人事評価・目標管理に特化した資料も無料でダウンロードできます。