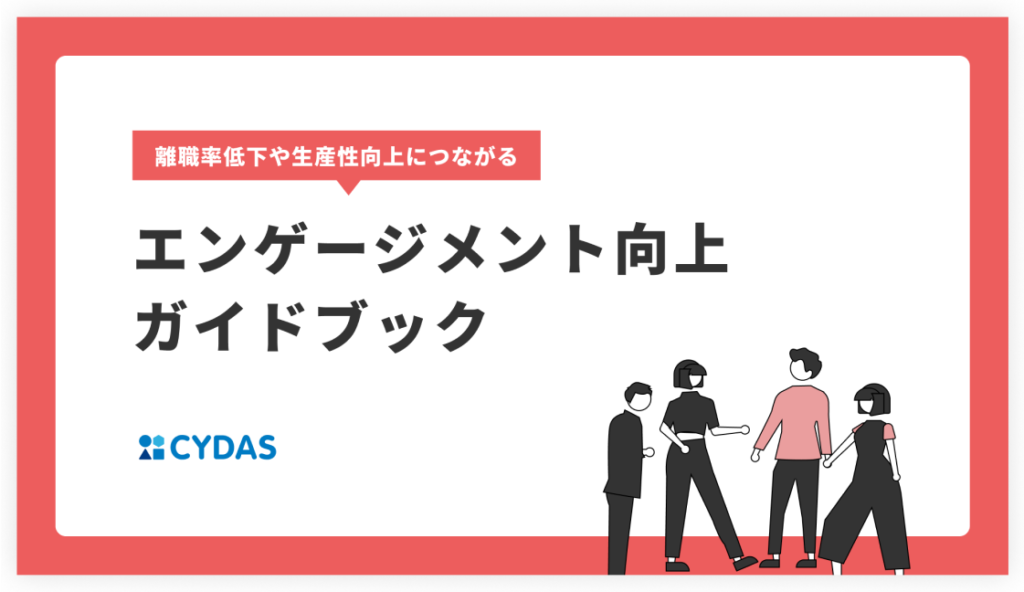2023.6.9
【わかりやすく解説】アドラー心理学入門。仕事や生き方に役立つ哲学
アドラー心理学は、『嫌われる勇気』などの書籍で一躍注目を集めるようになった心理学です。アドラー心理学を学び、日常生活や仕事に活用することで、自分の行動や他人との関わり方に良い変化をもたらす可能性があります。
本記事では、アドラー心理学の特徴や思想、職場での活用方法とメリットなどについて詳しく解説します。アドラー心理学を学習するのに適したおすすめの書籍も紹介しますので、ビジネスにおけるアドラー心理学の活かし方を知りたい方はぜひご覧ください。
働きがいのある組織づくりを推進するなら、タレントマネジメントシステム「CYDAS」
アドラー心理学とは

アドラー心理学とは、オーストリア人精神科医であるアルフレッド・アドラー(Alfred Adler)氏が提唱した心理学です。海外では「個人心理学」などとも呼ばれ、人間の心と行動の問題を解決に導くための知識に加えて、実践的な考えを打ち立てています。
アドラー氏は、「個人の精神生活は、属する共同生活、つまり社会の在り方と強く結びついている」と考えます。その前提を踏まえ、アドラー心理学では「社会と調和して暮らすこと」「私には能力があるという意識をもつこと」「人々は私の仲間であるという意識を持つこと」が人生の基本目標であるとし「目標達成に向けて人はいかに生きるべきか」ということを体系化しています。
アドラーとフロイトの違い
アドラーと同様に、世界的に有名な心理学者に「フロイト」がいます。フロイトもアドラーと同じオーストリアの精神科医で、精神分析学の創始者として知られており、夢分析の分野でも名を残しています。
フロイトは「人間は、過去の経験が原因となって今の行動が規定される」という「原因論」を提唱しました。アドラーは、かつてはフロイトとともに研究していたのですが、意見の相違から決別することとなり、アドラー心理学を構築するに至っています。
フロイトの心理学では「過去のトラウマや無意識の欲求が、個人の行動や感情に大きく影響する」と説くのに対し、アドラー心理学では「今の目標や価値観が個人の行動や人格形成に影響を与える」と考えます。
アドラー心理学が人気になった背景
アドラー心理学が広まった背景には、岸見一郎氏と古賀史健氏の共著である『嫌われる勇気』 のヒットが挙げられます。『嫌われる勇気』 は、2013年に書籍が出版された後、TVドラマ化され、幅広い世代に浸透していきました。
また、SNSの浸透もアドラー心理学の人気を後押ししています。SNSがコミュニケーションツールとして必須となった現代では、他人との比較や承認欲求が加速し、「自分らしさ」に疑問を持つ人が増えてきました。
また、あらゆる方向への気遣いを配慮することが求められるなど、SNSを通して疲弊する人が自分とまっすぐ向き合う方法を探し始めたことも影響しています。
アドラー心理学の特徴 。5つの理論と行動例

アドラー心理学は、以下の5つの理論から成り立っています。
- 目的論
- 全体論
- 認知論
- 対人関係論
- 自己決定性
アドラー心理学の理論的な枠組みである上記5つの理論を理解する必要があります。ここでは、それぞれの理論について見ていきましょう。
目的論
目的論とは「人間の行動にはすべて目的がある」という理論です。「人は自ら定めた目的に向かって動いていく」という前提があり、「自分の目的を達成するために自らが選択した結果、自分が現在置かれている状況がある」と考えます。
目的論に基づく行動例としては「子どもが寝る前に電気を消すと泣く場合、暗闇が怖いからではなく、母親の関心を引くという目的のために、暗闇を利用して「怖い」という感情を作り出している」というものが挙げられます。
全体論
全体論とは、「人は、心の中が矛盾対立する生き物ではなく、1人ひとりかけがえのない、分割不能な存在である」という捉え方です。人間は精神、意識・無意識、肉体といったすべての要素において「分割できない存在」であると考えます。
全体論を元にした行動例は、「プレゼンで物怖じせずに堂々とパフォーマンスするために、メンタルを強くしたい場合に、心だけでなく、話すスキル(技)や体力(体)を改善する対策を実践する」ことです。これは、自分が他の要素が相互作用し合う「統一体」として捉える例です。
認知論
認知論とは「人は、自分流の主観的な意味づけを通してしか物事を把握できない」という理論です。人間は、事実をありのままに客観的に把握することは不可能であり、同じ出来事を体験したとしても、感じ方や受け止め方は人それぞれ異なります。
つまり、人は事実そのものではなく、事実の「解釈」を体験していることになり、「起きたことをどのように解釈するかで、現実や体験を変えることができる」と提唱しています。
認知論の行動例としては「水が半分入ったコップを見て、「半分も残っている」と捉えるか「半分なくなってしまった」と捉えるか」という問いが挙げられます。
対人関係論
対人関係論とは「すべての行動には相手役がいる」という考え方です。人の行動や感情には必ず相手が存在していて、相手の行動に対して自分が感情や行動を返し、相手はさらに行動を示す、というように、お互いに影響を与え合って生きています。言い換えると、「人間の悩みのすべては対人関係の悩みである」と捉えることができます。
対人関係論の例としては、「良い人間関係を構築していきたい」と思っている社員ほど相手を観察し、「相手のためになにができるのか?」と考える傾向がある、というものです。「自分の悩みは他者の影響により発生する」と捉え、行動しようとします。
自己決定性
自己決定性とは「自分のすべての行動は自分自身で決めることができる」という考え方です。自分ではコントロールできない悩みや課題があっても、「置かれた環境をどう捉え、どのように対応するのか決めるのは自分自身である」と捉え、主体性や独自性を持つことが大切だとしています。
アドラーは、「人は誰しもが自分の運命の主人公」だと言います。育ってきた環境や先天的な要素など「〜〜のせいで不幸だ」と嘆くのではなく、そうした影響の解釈をどのように変え、どう行動するかを決めるのは自分自身なのです。
アドラー心理学の思想
アドラー心理学は、先述した5つの理論の上に、思想や概念が成り立っています。ここでは、「劣等感」「課題の分離」「勇気づけ」「共同体感覚」という4つの思想について詳しく解説します。
劣等感|自己実現に利用する
劣等感とは「他人と比べて自分が劣っていると感じること」を指します。アドラーは自身の体系から「人には劣った点を補おうとする力が備わっている」と考えるようになりました。
アドラー心理学では、「劣等感」を持つことは悪いことではなく、「理想の自分に近づくために劣等感を利用する」ことを提唱しています。
例えば、恋人に「仕事がうまくいっていない(年収が低い)」といった理由でフラれた際に、「自分は稼げないダメな人間だ」と落ち込むのではなく、劣等感を利用して「年収を上げるためにスキルアップしよう」という考えを持ち、行動に移すことが挙げられます。
課題の分離|他人の課題を切り離す
課題の分離とは、「自分と相手の課題を分離して考える」思想です。アドラー心理学の理論では「自分の課題解決という目的を持って生きる」ことに加えて、「他人の課題に勝手に介入してはいけない」と説いています。
他者が持っている課題と自分の課題を分離させることで、「これは他者の課題だ」と判断し、他者に介入しすぎないようになります。
例えば、部下に間違いを注意する際に、「相手を傷つけない言い方はないか」「注意して嫌われないか」など、相手がどう思うかを考えてしまうことがあるでしょう。そこで、課題の分離に従うと、上記はすべて相手の課題と捉えます。そして「相手の課題を自分がコントロールすることはできない」と割り切ることができるのです。
勇気づけ|困難を乗り越える力
アドラー心理学は「勇気の心理学」とも呼ばれ、勇気づけは、アドラー心理学の核となる思想です。勇気づけとは「課題を乗り越えるための内なる活力」のことを指します。勇気付けによって、自分の考え方や行動が変わり、目的達成や悩みの解消につながっていきます。
勇気づけは、自分だけでなく他者に対しても有用で、他者が自分自身の力で生きていけるようサポートすることも含めて解釈されています。また、先述した「劣等感」の克服に挫折してしまった場合にも、「困難を乗り越える活力を与えること」「困難に立ち向かうための精神的な能力を身につけること」といった勇気づけが効果的です。
共同体感覚|他人を尊重する
共同体感覚とは、一言で言うと「自分は共同体の一部(周りと繋がっている感覚)である、と主観的に感じる思想」、または「他人へ関心を向けること」を意味します。「学校」「職場」「家族」などの中で、自分はその一員であるという感覚を持っている状態です。
共同体感覚には「相手を無条件に信頼する」「そのままの自分を受け入れる」「他人の役に立つ行いをする」という3つの思想が重要だと言います。対人関係論の理論にあるように、アドラーは「人はもともと誰かとつながりたいと切望する存在である」と考え、「共同体感覚を持ちながら他人を尊重し幸せにすることが、自分の幸せにもつながる」と説いています。
アドラー心理学が職場におよぼす影響

アドラー心理学を取り入れることで、ビジネスや職場においてさまざまな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、アドラー心理学がもたらす代表的な2つの影響について説明します。
主体的に考えるようになる
アトラー心理学を採用することで、「主体的に考え行動する人材が育成できる」という効果が期待できます。目の前の課題を自分ごととして捉え、解決策を考え能動的に行動するような自走力を育むことにつながります。
例えば、大きな商談の日に重大なミスを犯してしまい、それ以降、商談の前日は心配で寝付けず、仕事の成績も低迷気味だったとします。これは、過去の失敗に捕らわれて「同じ間違いを繰り返してしまうだろう」と思い込んでしまっている状態です。
そこで、アドラー心理学を用いると、過去にミスをしたという「劣等感」を自己実現のために利用すると決め、克服するためにどんな「勇気づけ」が有効かと視点を変えることで、目的達成に向けて行動できるようになります。
人間関係のストレスが減る
アドラー心理学は、職場における人間関係のストレス軽減に役立ちます。「認知論」では、「相手の意見が自分と異なっていることは、自分を嫌っていることが原因ではない」ことを明確にしています。「課題の分離」を用いて、自分と相手とを分けて捉えることで、必要以上に他人に介入しなくなり、ストレスが減ります。
例えば、ミスした部下に対して大声で怒鳴る上司が、朝から不機嫌だったとします。上司の様子を見るだけで恐縮してしまい、「もしかすると自分のミスが原因かも」といった考えが浮かんできたとしても「上司の課題であって自分の課題ではない」と割り切ることで、自分の気持ちを保てるでしょう。
また、「共同体感覚」の概念により、対等に尊重しあう意識を持ち、横の人間関係を意識した職場のコミュニケーションが活性化する効果も期待できます。
アドラー心理学を学ぶのにおすすめの本
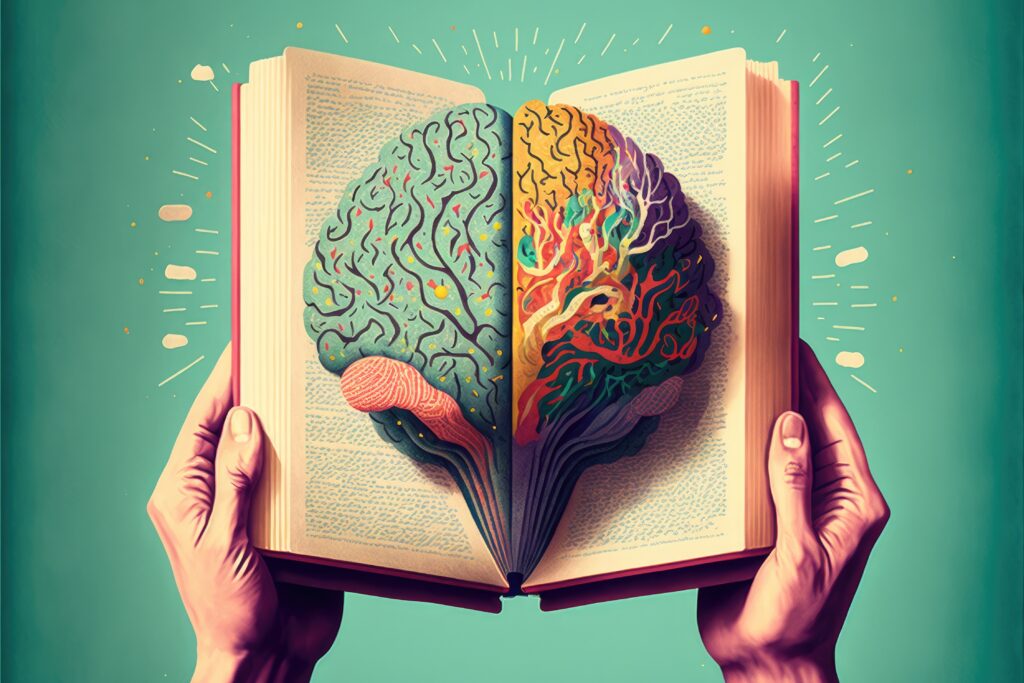
アドラー心理学に関する書籍は、多数出版されています。初めてアドラー心理学に触れる人でも理解しやすい入門書を含めて、おすすめの書籍をピックアップして紹介します。
『アドラー心理学入門』岸見一郎
『アドラー心理学入門』は、日本におけるアドラー心理学の第一人者である「岸見一郎」の単著です。アドラー心理学の基本的な考え方や実践についてわかりやすく紹介しており、アドラー入門書として最適な1冊といえます。
1999年のリリース以降、多くの読者に親しまれており、現在はオーディオブックも出ています。「どうすれば幸福に生きることができるか」「どのように生きて行けばいいのか」といった問いに対するアドラー心理学の方針を知ることができます。
『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』岸見 一郎 ・古賀 史健
『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』は、いずれも岸見一郎氏とライターである古賀史健氏の共著です。『嫌われる勇気』は世界的ベストセラーとなっており、この本を通してアドラー心理学を知った人も多いでしょう。
『嫌われる勇気』では、「勇気づけ」「課題の分離」などの思想について詳しく解説されています。対話形式でまとめられており、読み進めやすい点も特徴です。
『幸せになる勇気』は、自分から人を愛する大切さについて学べる1冊です。「他人が自分を愛してくれるかは他人の課題である」「自分は人を愛することしかできない」と気付かされる構成になっています。
『マンガでやさしくわかるアドラー心理学』
『マンガでやさしくわかるアドラー心理学』は、アドラー心理学を漫画で簡潔に学べる書籍です。著者は臨床心理士の八巻秀氏で、イラストや図などを使いながらわかりやすく解説しています。
ストーリー形式のためポイントが理解しやすく、心理学の世界に馴染みのない人でも気軽に手に取れるでしょう。
まとめ
アドラー心理学は、心理学の世界三大巨匠であるアルフレッド・アドラー氏による思想です。「課題の分離」や「勇気づけ」といった思考により、自分が持っている解釈や視点を変え、主体性を持って理想や目的に向かって行動することを後押ししています。
アドラー心理学を学ぶことで、悩みや課題の解消やブレイクスルーのきっかけになる上、ビジネスでの人材育成や職場での人間関係の円滑化にもつながります。今回紹介したおすすめ書籍も参考にして、アドラー心理学を理解し、日常業務に活かしていきましょう。
働きがいを応援するメディア「ピポラボ」では、人事・経営層・ビジネスパーソンが押さえるべきキーワードについて解説しています。運営会社・サイダスが提供するタレントマネジメントシステム「CYDAS」については、無料ダウンロード資料やサービスサイトをご確認ください。お役立ち資料も多数取り揃えています!