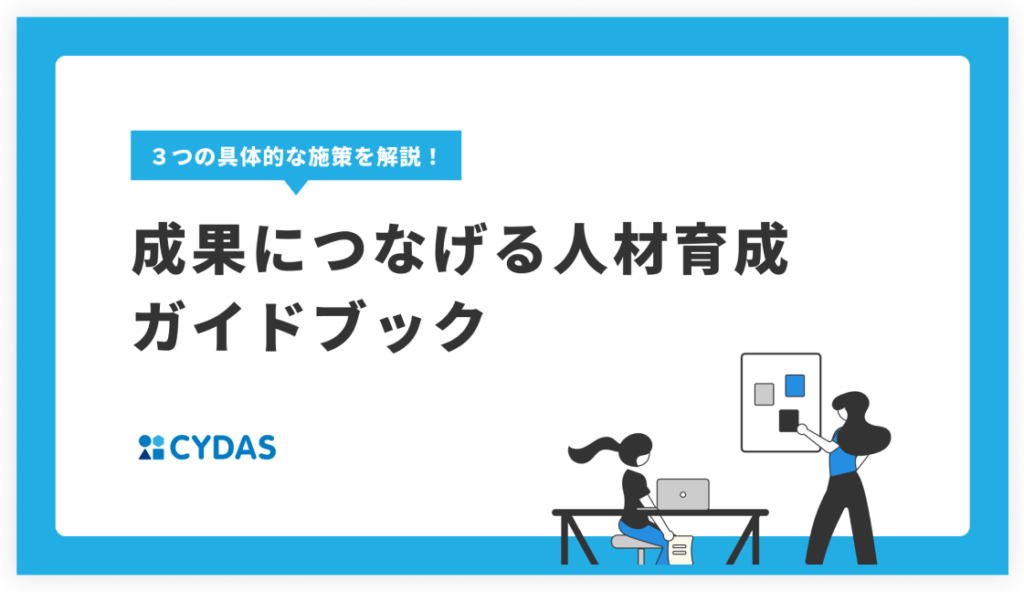2022.5.17
コンピテンシーとは?スキルや能力との違い、導入のメリットについて解説
人事業界でよく耳にする「コンピテンシー」は、近年ますます注目を浴びている言葉です。しかし、なぜ注目されているのか、活用するとどんなメリットが得られるのか、いまいち理解できていないという人も少なくありません。コンピテンシーと似た用語も幾つかあるので、混同してしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、コンピテンシーについて正しく理解できるよう、スキルや能力との違いや概要について詳しく解説します。活用するメリット・デメリット、さらには導入する手順まで紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
サイダス社が提供する「CYDAS」は、「働きがい」を生み出すメカニズムが詰まったタレントマネジメントシステムです。人材情報を一元化し、目標管理や1on1、フィードバック機能など、さまざまな機能を組み合わせてサイクルを回すことで、一人ひとりのワークエンゲージメントを高め、組織を強くします。

目次
コンピテンシーの意味とは?

コンピテンシーとは、「能力」という意味を持つ言葉です。今回説明するコンピテンシーは人事業界で使われる用語であり、企業において高い業績をおさめたり、優秀な成果を上げたりしている人の行動特性のことを指します。
成績のよい社員には、「成功したときの理由を探る」「立てた目標は必ず達成する」など、高い業績に結びつく行動特性があるものです。この共通する行動特性を分析して見える化することで、組織や部門に合ったコンピテンシーが設定できます。
コンピテンシーを活用することで社員全員が成長し、生産性の向上につながるというメリットがあるため、近年ではコンピテンシーを評価制度に取り入れる企業が増えています。
また、コンピテンシーは採用活動の場においても取り入れられているのが特徴です。コンピテンシーを採用現場に取り入れることで、自社に適した人材かどうか判断しやすくなりる上に、評価を統一できるため面接担当者による評価のブレが防げます。
コンピテンシーと似た用語との違い
コンピテンシーには、似た用語が幾つかあります。今回は、とくに間違えやすい以下3つの用語とコンピテンシーとの違いについて解説します。
- スキル
- コア・コンピタンス
- アビリティ
混同しないよう、しっかりチェックしておきましょう。
コンピテンシーとスキルの違い
スキルとは、専門的な知識や技術、技能そのもののことを指します。何を知っているのか、どんなことができるのかなど、保有するスキルによって決まるのが特徴です。
例えば、法律に関する専門知識というスキルを持っていれば、法に基づいたアドバイスができます送れます。ただし、相談を持ちかけられなければ、そのスキルが発揮されることはないでしょう。
一方のコンピテンシーは、知識や技術をどのように使おうとするか、どのように用いてどうするかという行動や思想のことを指します。仮に高度なスキルを持っていても、何かしらの行動をとらなければ高い成果は上げられません。
企業にとって重要なのは、自身がもつスキルを活かし、成果につながる行動ができるかどうかです。そのため、近年ではコンピテンシーを重視した評価制度が注目されています。
スキル
個人が保有する専門的な知識・技術・技能を意味します。例としては、営業力、プログラミング知識、法律に関する専門知識、などが挙げられます。
コンピテンシー
スキル(能力や知識)を発揮する力を意味します。例としては、素直さ、目標達成意欲、第一印象度、統率力、などが挙げられます。
コンピテンシーとコア・コンピタンスの違い
コア・コンピタンスとは、企業が強みとする技術や特色のことです。競合他社から模倣されない力、顧客に満足してもらえる能力や技術などを指します。具体例として、ホンダのエンジン技術やシャープの液晶技術などが挙げられます。
そして、コンピテンシーとコア・コンピタンスの違いは、対象となるものが「個人」になるのか、「組織」になるのかという点です。コンピテンシーは個人を対象にしていますが、一方のコア・コンピタンスは組織を対象としています。
優秀な社員が成果を上げる行動をとり企業に貢献する力をコンピテンシー、組織が顧客や社会のために能力を発揮する力をコア・コンピタンスだと覚えておくとよいでしょう。
コンピテンシーとアビリティの違い
アビリティとは、能力や技能そのもののことです。ただし、同様の意味をもつスキルほど高度なものではなく、持っている力量のようなものを指します。
努力して身に付けた後天的な能力・技能をスキル、生まれつき身に付いている先天的な才能・技能をアビリティと覚えておくとよいでしょう。
コンピテンシーとの違いは、「能力や技能そのもの」か「能力や技能を発揮する力」なのかどうかです。アビリティは前者の「能力や技能そのもの」を指します。
コンピテンシー評価のシステム化は、タレントマネジメントシステム「CYDAS」にお任せ!
コンピテンシーが注目を浴びている理由

コンピテンシーは1980年代にアメリカで生まれ、1990年代初期から広まった考え方です。
米国文化情報局からの依頼を受けたハーバード大学のデイヴィッド・C・マクレランド氏が、業績をおさめる社員の特性について調査を行ったところ、学歴は業績の高さにほとんど相関がないという結果になりました。
さらに、高い成果を上げる社員には共通した行動パターン、価値観、考え方、性格があることが分かったのです。この調査結果を踏まえ、優秀な成績をおさめる社員の行動特性を分析してモデル化し、評価基準に落とし込むコンピテンシーが確立しました。
日本で注目されるようになったきっかけは、評価制度が年功序列から成果主義に転換したことです。1990年前半まで日本での評価制度は、勤続年数が長い人ほど評価される年功序列型が基本でした。
しかし、バブルが崩壊し企業競争が激しくなったことや、少子高齢化による労働者の減少などが影響し、「労働量」よりも「労働の質」が重視されるようになったのです。
企業として高い成果を上げていくためには、社員一人ひとりの行動の質を高めていく必要があるという背景の中で、客観的かつ公平に評価できるコンピテンシーが注目を浴びるようになりました。
コンピテンシーの活用方法
コンピテンシーが活用できる場面は、以下の3つです。
- 人事評価制度
- 採用活動
- 人材育成
それぞれ効果的に活用できるよう、詳しく解説します。
人事評価制度に取り入れる
近年、コンピテンシーを人事評価に導入する企業が増えています。コンピテンシーは、企業において高い成果を上げている社員をロールモデルとし、どんな行動特性があるのかを洗い出して指標を決めるので、人事評価の基準が明確になるのが特徴です。
人事評価する際は、指標に基づいて行動できたかで評価するため、評価者の主観に捉われず、ブレのない評価がつけられます。企業が社員に求めることは、高いスキルを活用して成果を上げてもらうことです。
社員が自ら行動するよう促す意味でも、人事評価制度にコンピテンシーを活用する企業が増えています。
コンピテンシー評価についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
採用活動に取り入れる
コンピテンシーは、採用基準を明確にする指標の一つにもなります。事前に、自社で活躍する社員のコンピテンシーをモデル化し、採用基準を設定することで、入社後に活躍できる人材かどうかを判断しやすくなるのがメリットです。
面接では「直近1年以内に成果を上げたエピソード」や「どのような成果を上げることができたのか」などを質問することがポイントです。
その上で、「成果を上げるためにどのような行動をしたのか」「なぜその行動をとったのか」を深掘りすると、採用候補者のコンピテンシーが明確になり、自社のコンピテンシーと照らし合わせることができます。これにより、自社が求める人材かどうかを判断しやすくなるのが特徴です。
さらに、コンピテンシーを採用活動に取り入れることは、面接官や採用担当者による評価のバラつきの軽減にもつながります。採用基準に沿って評価されるので、印象や感覚といった主観的な評価が少なくなります。採用に関わる社員が共通認識をもって対応できるので、自社に合った人材の見落としも防げるでしょう。
人材育成に取り入れる
コンピテンシーは、優秀な人材を育成する際にも役立てられているのが特徴です。自社で高い成果を上げている社員の行動特性を示すことで、「どのように考えて、どのような行動をとると結果につながるのか」を社員に伝えることができます。
さらに、示した行動特性をもとに、コンピテンシーに基づいた目標を設定してもらうことも重要です。目標設定することでやるべきことが明確になり、成果を上げるために努力しようと思える環境が作れます。積極的かつ自発的な行動が促されるので、優秀な人材を効率よく育成することが可能です。
コンピテンシーを活用すると、高いモチベーションを維持しやすいといったメリットもあります。例えば、上司から「もっとやる気を出せ」「誠意を見せろ」と注意されても、曖昧過ぎて何をどう改善すべきか分かりません。
しかし、コンピテンシーによって行動特性が示されていれば、やるべきことが具体的に理解できるので、社員一人ひとりが納得のいく行動指針を立てられます。
成果につながる人材育成の手法が学べるガイドブックはこちら!
人事評価制度にコンピテンシーを活用するメリット

人事評価制度にコンピテンシーを活用すると、以下4つのメリットが生まれます。
- 優秀な人材が効率良く育成できる
- 社員が目指すべき目標が明確化し行動しやすくなる
- 社員の納得感や公平性が高まる
- 評価者側の負担が軽減される
社員のモチベーション向上や、人事評価の負担軽減にもつながる重要な部分です。一つずつチェックしていきましょう。
優秀な人材が効率良く育成できる
コンピテンシー評価では、優秀な人材を効率良く育成できるのがポイントです。コンピテンシー評価には、実際の業務に即したロールモデルが存在しています。ロールモデルが評価基準になっていれば、社員は企業が求めていることを明確に理解することが可能です。
求められていることが分かれば自ずとやるべきことが見えてくるため、自発的な成長を促して即戦力のある人材が育成しやすくなります。また、課題点も可視化されるので、自分では気付きにくい欠点にも気付くことができ、改善・成長してさらに企業へ貢献してくれるはずです。
社員が目指すべき目標が明確化し行動しやすくなる
コンピテンシー評価では目指すべきロールモデルが明確化されているため、目標に向かって行動しやすくなるのが特徴です。
例えば、成果を上げている社員には「さまざまな情報源にアクセスしている」「指示される前に行動ができている」などの特徴が共通して見られます。コンピテンシー評価ではこれらの特性が明確に定まっているため、各社員が自らどのように行動すればよいのかを考えて実行することができるようになります。
「積極性をもって取り組むこと」と言われると具体的な行動に移すことが難しくなってしまいますが、コンピテンシー評価では社員が迷わず目標に向かって努力することができるので、高いモチベーションを維持しやすくなるのがメリットです。
社員の納得感や公平性が高まる
コンピテンシー評価において評価基準となるものは、具体的な行動です。協調性や責任感など抽象的なものではなく、客観的な指標のもとで評価されるので、社員の納得感が高まります。また、評価者側による主観的な意見が評価に反映されにくくなるのもメリットです。
公平性の高い評価がつけられるので、企業に対する信頼感や社員のモチベーション向上にもつながるでしょう。
評価者側の負担が軽減される
コンピテンシー評価では、ロールモデルとして定めた行動基準を満たしているかそうでないかで評価できるため、評価者側が評価しやすくなります。
従来主流となっていた職能資格制度(能力評価)は、評価基準が曖昧であったため、主観に左右されやすいという問題がありました。これにより、社員からの納得感が得にくく、時間をかけてつけた評価が不満の原因になることも珍しくありませんでした。
その点、コンピテンシー評価は「しているか」「していないか」で判断できるので、答えが明確な分、評価しやすいのがメリットです。社員からも納得感を得られやすく、不満が生まれにくいところも評価者側の精神的負担軽減につながるでしょう。
採用活動にコンピテンシーを活用するメリット

採用活動にコンピテンシーを活用するメリットは、以下の3つです。
- 面接官による評価のバラつきが防げる
- 自社が求める人材を明確に提示できる
- 採用活動の負担を軽減できる
企業の今後にも関わる重要な項目です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
面接官による評価のバラつきが防げる
コンピテンシーを定めておくことで、自社の求める人材が明確になることがメリットです。面接時には、印象や感覚といった主観的な評価も大切ではあるものの、そこを重視してしまうと面接官によって評価にバラつきが生じやすくなります。
誰の意見を尊重するべきか迷ったり、望ましい人材を見落としたりする可能性もあるでしょう。コンピテンシーがあることで、面接官は基準に沿って評価を行えばよいので、評価のバラつきが最小限に抑えられます。
また、コンピテンシーの活用は、新しく採用担当者を配置した場合にも効果的です。採用基準の項目が明確にそろっているので、より早くキャッチアップができます。経験不足による評価のバラつきも防げるのがポイントです。
自社が求める人材を明確に提示できる
応募者に対して、自社がどんな人材を求めているのか明確に提示できるようになるのもメリットです。応募者は、自分が求められている人材かどうか判断しやすくなるので、満足度が上がったり企業をより理解してもらえたりする効果が期待できます。
入社後にどのような行動が求められるのかを把握してもらえるので、入社前と後のギャップが埋められるのも魅力です。企業にとっては、早期離職のリスク軽減にもつながります。
採用活動の負担を軽減できる
コンピテンシーの活用は、採用担当者の負担軽減にもつながるのが特徴です。コンピテンシーに基づいた質問項目や評価項目を事前に定めることができるため、面接で何を聞けばよいのか分からない、どういう答えが評価に値するのか分からない、という事態が防げます。
とくに、採用担当者のスキル不足が課題となっている企業にとっては効果的です。例えば、コンピテンシーを活用していない面接では、学歴や資格、志望動機、さらには見た目などから、自社に適した人材かどうか判断しなければいけません。
これでは表面しか見えていないので、採用担当者にスキルがなければ、適していない人材を採用してしまうこともありえます。コンピテンシーの活用により、採用基準が統一されることで、採用担当者は客観的に評価を付けられるようになり、自社に適した人材を見抜きやすくなるのがポイントです。
コンピテンシーを活用するデメリット

コンピテンシーには魅力的なメリットが複数ある一方で、以下2つのデメリットがあります。
- コンピテンシーを定めるのが難しい・時間がかかる
- 手間のかかるアップデートが不可欠
コンピテンシーを導入するべきか否かを検討する項目になるので、メリットと比較しながらチェックしてみてください。
コンピテンシーを定めるのが難しい・時間がかかる
コンピテンシーには正解がなく、効果的なものにするためには自社独自の基準で設定しなければいけないため、定めるのが難しく時間もかかります。
まずは、成果を出している社員のピックアップ、そしてヒヤリングした内容を言語化して社員に分かりやすくまとめて共有する作業が必要です。また、ロールモデルとなる社員が、必ずしも成果を上げている理由を自分で認識しているとは限りません。
認識していない場合は、ヒヤリングをしてもコンピテンシーの指標につなげることが難しくなります。さらに、コンピテンシーは全職種・全役割において定めなければいけません。複数の社員にヒヤリングする必要があるので、設定に時間がかかります。
手間のかかるアップデートが不可欠
コンピテンシーは、設定した後も小まめにアップデートする必要があります。基準が明確で細分化して決められている分、柔軟性に乏しく事業内容や業務内容などの変化に対応するのが困難です。
時代や市場の変化によって、企業側でも業務内容や組織図、経営体制などは変わるものなので、その都度アップデートや修正、ときには試行錯誤も必要になってしまいます。また、コンピテンシーをアップデートした後は、社員に浸透させなければいけません。そこにも時間と手間がかかるので、担当者の負担は増えるでしょう。
コンピテンシーのモデルを作成する上で参考になる型
コンピテンシーには、目標とするモデル作成が必要です。その際、参考になるのが以下3つの型です。
- 実際の社員をモデルにする「実在型モデル」
- 理想とする人物像を作る「理想形モデル」
- 上記2つを組み合わせた「ハイブリッド型モデル」
自社に適したコンピテンシーのモデルを作成できるよう、チェックしておきましょう。
実際の社員をモデルにする「実在型モデル」
実在型モデルは、自社で成果を上げている社員をロールモデルとして作成する、3つの中で最も主流の型です。実態に即したモデルが作成できるので、比較的実用性のある型だと言えます。
また、イメージをつかみやすいので現場にも取り入れやすく、スムーズな導入が可能です。ただし、実在型モデルをベースとする場合は、ほかの社員でも達成しうるものなのかを慎重に検討する必要があります。
難易度が高いと、モチベーションを下げる要因にもなり兼ねません。さまざまな社員にあてはめて策定していくことが重要です。
理想とする人物像を作る「理想形モデル」
理想形モデルは、自社が理想とする人物像を策定し、その人物像の行動特性を抽出してコンピテンシーを定める手法です。企業理念や事業戦略などから、どのような思考をもって行動できる人物を求めるのか策定します。
実在する社員の行動を洗い出したり、ヒヤリングしたりする必要性がないので、実在型モデルよりも難易度は低いのが特徴です。また、起業したばかりでロールモデルとなる社員がいない企業でも導入しやすいでしょう。
ただし、現実に即したものにする調整が難しく、理想を追い求めすぎると現実的ではないモデルが作成されかねません。ハードルが高すぎると、社員のモチベーションが低下する恐れがあるので、うまく調整できるかどうかがポイントです。
上記2つを組み合わせた「ハイブリッド型モデル」
ハイブリッド型モデルは、実在型と理想形のメリットを組み合わせた手法です。
企業理念や事業戦略などの理想から逆算して考えたものから、実態に即していないものを取捨選択してモデルを作成します。
実用的でありつつ、作成難易度が下がるので、コンピテンシーを初めて導入する企業におすすめです。
コンピテンシーを導入する手順
最後に、コンピテンシーを導入する手順をチェックしておきましょう。ポイントを踏まえながら解説するので、効率よく進めたい人は参考にしてみてください。
【コンピテンシーを導入する手順】
- 高い成果を上げている社員へヒヤリングを行う
- ヒヤリング内容からコンピテンシーを抽出する
- 企業のビジョンと照らし合わせて取捨選択する
- 取り入れるコンピテンシーを選定する
- 選定したコンピテンシーをレベル分けする
- テスト・調整をして完成させる
高い成果を上げている社員へヒヤリングを行う
まずは、自社で高い成果を上げている社員(ロールモデル)を選び、ヒヤリングを行います。ヒヤリングする際は「なぜ成果が上がっているのか」「どんな行動をしているのか」など、細かく深堀りすることが重要です。
ただし、対象社員が自分で分かりやすく言語化できるとは限らないため、担当者が上手にヒヤリングしなければいけません。また、対象社員が何気なく行っている行動が、成果につながっている場合もあります。
同僚や上司、部下などにもヒヤリングを行い、対象社員の仕事ぶりを観察するのも有効です。対象社員自身が気付けていない行動特性を見つけられるかもしれません。
ヒヤリング内容からコンピテンシーを抽出する
次に、ヒヤリングした内容を振り返り、コンピテンシー(行動特性)を抽出しましょう。このとき、コンピテンシーディクショナリーで定義されている評価項目と照らし合わせると、コンピテンシーを絞り込みやすくなります。
とはいえ、コンピテンシーは自社独自の基準で設定しなければ効果的なものにはなりません。そのため、コンピテンシーディクショナリーの評価項目は、あくまでも参考程度に留めておくことがポイントです。自社にとって必要だと思われる行動に絞って抽出しましょう。
コンピテンシー・ディクショナリーとは?
コンピテンシー・ディクショナリーとは、コンピテンシーをモデル化するときに、ベースとなる評価項目をリスト化したものです。1990年代に、ライルM.スペンサーとシグネM.スペンサーによって開発されました。
コンピテンシーの評価項目群には、「達成とアクション」「支援と人的サービス」「インパクトと影響力」「マネジメント・コンピテンシー」「認知コンピテンシー」「個人の効果性」の6つの領域を大枠とし、そこからさらに20項目に細分化し分類されています。
ヒヤリングで分析した内容をコンピテンシー・ディクショナリーの評価項目に落とし込むことで、成果につながる行動特性を網羅的に汲み取れるようになるのです。
評価項目の分類は、組織や部門に適していないと効果を発揮できません。コンピテンシーを抽出する際は、自社にあった評価項目の分類をすることが重要です。
企業のビジョンと照らし合わせて取捨選択する
抽出したコンピテンシーを、企業のビジョンやバリュー、ミッションなどと照らし合わせます。必要なものは残しますが、企業のビジョンなどと合致しないものは、行動特性としてふさわしくないので排除してください。
この段階では、企業のビジョンなどと合致しているものはすべてピックアップしておきましょう。多少数が多くても、この後の工程で数をしぼるので問題ありません。
取り入れるコンピテンシーを選定する
すべての項目を取り入れてしまうと運用が大変になってしまいます。取り入れるものと取り入れないものとを分類しましょう。
分類するときのポイントは、選定したコンピテンシーの中でもとくに成果をあげるために重要なものや、企業が大事にしたいものを選ぶことです。
企業のビジョンなどと合致していても、優先度や重要度が低いものは排除することで、運用の負担を軽減できます。
選定したコンピテンシーをレベル分けする
次に、選定したコンピテンシーをレベル分けしましょう。レベルは3〜5段階くらいに分けると、細かすぎずちょうどよいと言われています。
新入社員に目指してほしいもの、中堅社員に目指してほしいもの、ベテラン社員に目指してほしいものなど、立場や役職ごとに分けると評価しやすくなります。
また、レベル分けをするときは、各評価項目の尺度も決めなければいけません。組織に共通する尺度がないと、評価が曖昧になってしまいます。評価項目に対してどのくらいできれば4なのか、3と4の評価基準の違いは何かなど、より具体的に設定するようにしましょう。
テスト・調整をして完成させる
レベル分けまでできたら、テストしてチェックを行います。まずは、企業で高い成績をおさめている社員の行動と、作成したコンピテンシーを照らし合わせてみてください。高い評価が得られるかを確認し、実態に即しているかをチェックしましょう。
また、成績が中程度の社員についても同じように評価してみて、高い成績をおさめる社員よりも評価が高くならないか確認します。
このように、複数人をサンプルとしてテストし、試行錯誤を繰り返すことで、より精度の高いコンピテンシーを策定できます。
コンピテンシー評価をシステム化するならCYDAS(サイダス)
コンピテンシーとは、高い業績をおさめる社員に共通してみられる行動特性のことです。自社に適したコンピテンシーを評価指標として活用することで、人事評価制度や採用活動においてさまざまなメリットが得られます。
評価制度が年功序列から成果主義に移行する企業が増えている今、コンピテンシー評価は多くの企業から注目されているものです。とはいえ、自社に適したコンピテンシー評価を策定するのは容易ではありません。
策定するまでには時間や労力がかかる上、導入した後も定期的なメンテナンスが必要です。抱えている業務と並行して導入・運用するのは、現実的に難しい企業も少なくないでしょう。
コンピテンシー評価の導入を前向きに検討したい人には、社員参加型の人材データプラットフォーム「CYDAS 」がおすすめです。CYDASは多様なツールを活かし、社員や人事、経営層まですべての人が働きやすい環境を作ります。
例えば、目標管理や評価は項目を簡単に設定できるので、その都度コンピテンシーに基づいた目標を設定できます。また、多面評価にも対応しているので、さまざまな観点から評価を受けた社員は、今後の目標を自発的に立てて成長しようと努力するでしょう。
今の人事評価制度を改善したい、社員の成長を促す環境を整えたいと考えている方人は、サイダスの資料をチェックしてみてください。